結論:助成金の「申請方法」は ①自分で申請 ②社労士に依頼 ③助成金コンサルに依頼 の3つだけ。
はじめに:助成金申請方法で迷う経営者が急増している
結論から言うと、助成金の申請方法は「自分で申請する」「社労士に依頼する」「助成金コンサルに依頼する」の3パターンしかない。ただしどの方法を選ぶかで、成功率・スピード・労力は大きく変わる。
2025年時点で中小企業を取り巻く環境は厳しい。最低賃金の引き上げ、人材不足、採用コストの高騰、そして設備投資にかかる費用増加。こうした背景から、「助成金を活用して資金を確保する」ことは事業拡大を目指す経営者にとって避けて通れないテーマになっている。
実際に厚生労働省が公表しているデータでも、主要助成金の予算は年々増加しており、特に「業務改善助成金」の申請件数は前年比で172%増加。採用投資や機材投資を計画している企業にとって、まさに今が活用のチャンスだ。
とはいえ「助成金 申請方法」と検索しても情報はバラバラで、制度の種類や要件が複雑すぎて結局どう動くべきかわからない経営者が多い。特に従業員5名以上を抱え、年商3億円を超えるような成長ステージの企業にとっては、社長自身が制度を調べて書類を作り込む時間などほぼゼロに等しい。
そこで本記事では、助成金申請の代表的な方法を3つ比較し、それぞれのメリット・デメリットを整理する。その上で「どの方法が効率的で、成功率が高く、事業拡大に直結するか」を社長目線で解説する。そして最後に、実際におすすめできる助成金コンサル会社3選を紹介し、筆者が最も信頼する(株)True Partnersをトップに挙げる理由をお伝えする。
1. 助成金の基本と注目度が高まっている背景
1-1. なぜ今「助成金」が重要か
助成金とは、国や自治体が企業の採用・教育・設備投資などを支援するために支給する返済不要のお金。融資とは異なり返済義務がないため、実質的に自己資金や利益と同じ価値を持つ。特に中小企業にとっては「資金調達の最後の砦」とも言える存在だ。
近年の最低賃金引き上げラッシュにより、人件費の負担は右肩上がり。さらにDX・AI導入や生産性向上投資へのプレッシャーも高まっている。こうした状況で助成金を活用できるかどうかが、事業拡大を続けられるか・停滞するかの分岐点になっている。
1-2. 主な助成金の種類
- 業務改善助成金:最低賃金引き上げと生産性向上投資をセットで実施する企業を支援
- 人材確保等支援助成金:採用・定着の仕組みづくり(テレワーク制度導入、勤務間インターバルなど)
- キャリアアップ助成金:非正規社員の正規雇用転換や処遇改善を行う企業向け
- 人材開発支援助成金:研修や教育プログラムに対する支援
これらの制度は「知っているかどうか」で明暗が分かれる。しかし多くの経営者は、助成金情報を調べる時間が取れず、結果的に数百万円〜数千万円単位の機会損失をしているのが現実だ。
2. 助成金申請方法おすすめ3選
助成金の申請方法は大きく分けて3つ。①自分で申請する、②社労士に依頼する、③助成金コンサルに依頼するという3パターンだ。それぞれにメリット・デメリットがあり、会社の規模や経営者のスタンスによって適した方法は変わってくる。
2-1. 自分で申請する場合
最もシンプルなのは、自社の経営者や管理部門が自分たちで申請書を作成する方法だ。厚生労働省のWebサイトや各都道府県労働局の案内を参考にしながら、必要な計画書・証拠書類を揃えて申請する。メリットは明確で、費用がゼロで済むことだ。
しかし実際には、就業規則や賃金台帳、雇用契約書など膨大な書類を要件に合わせて整備する必要がある。加えて「業務改善助成金」や「人材確保等支援助成金」といった制度ごとに申請条件が細かく異なるため、制度を読み解くだけでも時間がかかる。経営者自身がそこに時間を割くのは現実的ではなく、結果的に不備や要件の見落としで不支給になるリスクも大きい。
2-2. 社労士に依頼する場合
次に多いのは、顧問契約をしている社会保険労務士(社労士)に依頼する方法だ。社労士は労務・社会保険のプロであり、助成金申請業務にも精通している人が多い。メリットは、法令順守や制度解釈に強く、安心感があることだ。
ただし注意点もある。まず費用面で、顧問料に加えて申請ごとに成果報酬が発生するのが一般的。さらに、すべての社労士が助成金に積極的とは限らず、「給与計算や手続き業務が中心で助成金はあまりやらない」という事務所も多い。結果として、提案力やスピード感にはバラつきが出やすいのがデメリットだ。
特に従業員5名以上の企業で、採用投資や機材投資に積極的な社長にとっては、「ただ手続きを代行してくれるだけ」では物足りないケースも多いだろう。
2-3. 助成金コンサル会社に依頼する場合
最後が、助成金申請に特化したコンサル会社に依頼する方法だ。ここ数年で一気に注目度が高まり、検索すると「助成金コンサル」「社労士おすすめ」と並んで多くの情報が出てくる。最大のメリットは、助成金に特化したノウハウと成功率の高さにある。
コンサル会社は制度改正や最新の支給要件を常にキャッチアップしており、単なる申請代行ではなく「どの制度を組み合わせれば受給額を最大化できるか」「どのタイミングで申請すべきか」といった戦略的な提案が可能だ。また多くの会社が完全成果報酬型を採用しているため、経営者にとってリスクが小さい。
もちろん玉石混交で、経験の浅い会社や手数料が高すぎる会社も存在する。しかし正しく選べば、社長は本業に集中しながら数百万円〜数千万円単位の資金を獲得できるという圧倒的なメリットを享受できる。
2-4. 結論:事業拡大を狙うならコンサル一択
3つの申請方法を比較すると、費用ゼロの「自分で申請」は小規模・時間のある経営者には向いている。社労士依頼は安心感がある一方で、スピード感や提案力は事務所次第。これに対して、積極的に採用・設備投資を仕掛けたい年商3億以上の企業に最もフィットするのは「助成金コンサル」だ。
本記事の後半では、数ある助成金コンサル会社の中からおすすめ3選を紹介し、特に「True Partners」をNo.1に推す理由を解説していく。
3. 助成金申請における成功率を高める3つのポイント
助成金申請は「制度を知っているかどうか」だけでは勝負が決まらない。実際に申請しても、書類不備や要件不足で不支給になるケースは全体の3〜4割とも言われる。では、どうすれば成功率を高められるのか。ここでは、経営者が必ず押さえておくべき3つのポイントを解説する。
3-1. 計画書の説得力を高める
助成金申請では「なぜこの投資が必要で、どのような成果を生むか」を説明する計画書が必須となる。単なる形式的な文章ではなく、数字に基づいたロジックを示すことが重要だ。
- Before:現状の課題(例:離職率18%、生産性0.6%)
- 施策:最低賃金の引き上げ+業務改善投資(機材導入、システム化)
- After:離職率改善18%→8%、生産性向上0.6%→3.8%
例えば「業務改善助成金」を活用する場合は、賃上げ→投資→成果の因果関係を明確に書く必要がある。ここが曖昧だと「単なる賃上げ」扱いされて支給額が減額されたり、却下されるリスクがある。
3-2. 証拠書類の整備を徹底する
助成金審査では、提出する書類がすべての根拠になる。就業規則、賃金台帳、雇用契約書、勤怠記録などを最新の状態に整え、矛盾のない形にしておくことが必須だ。
よくある失敗は以下の通りだ。
- 就業規則が古く、実態と合っていない
- 賃金台帳と給与明細で金額が一致していない
- 勤怠記録が紙のままで欠損が多い
- 36協定が未締結で残業時間の管理が不十分
これらは審査官から見てすぐに突っ込まれるポイントだ。逆に言えば、ここを徹底的に整えておけば「信頼できる会社」として評価され、審査もスムーズに進む。助成金コンサルに依頼すると、こうした書類の抜け漏れチェックも一括でサポートしてくれるため、成功率が大幅に上がる。
3-3. スケジュール管理を徹底する
助成金申請のもう一つの落とし穴は「締切遅れ」だ。多くの制度は「事前着手NG」「公募期間限定」というルールがあり、1日でも遅れると申請そのものが無効になる。特に「業務改善助成金」などは予算枠が埋まると受付終了になるため、スピード感と計画性が欠かせない。
スケジュール管理で押さえるべきは以下の3点だ。
- 申請期限をガントチャートで可視化する
- 賃上げや設備投資の開始日を制度要件と照合する
- 実績報告の準備を申請時点から逆算して進める
助成金コンサル会社を利用するメリットの一つは、この進行管理を代行してくれる点にある。社長が「気づいたら期限切れ」というリスクを避け、本業に集中できるのは非常に大きな価値だ。
4. 【比較表】申請方法ごとの特徴まとめ
ここまで3つの申請方法を解説してきたが、「結局どれが自社に合っているのか?」を判断するために、特徴を一覧表で整理した。比較ポイントは費用・労力・成功率・スピード感の4軸だ。
| 申請方法 | 費用 | 労力 | 成功率 | スピード感 |
|---|---|---|---|---|
| 自分で申請 | 0円 | 非常に高い(社長・管理部が膨大な作業を担当) | 低い(要件見落としや書類不備が発生しやすい) | 低い(慣れない作業で時間がかかる) |
| 社労士に依頼 | 顧問料+成果報酬(総額数十万円〜) | 中程度(手続きは任せられるが資料準備は必要) | 中程度(社労士ごとの得意不得意に依存) | 中程度(顧問業務の合間に対応するケース多い) |
| 助成金コンサル会社に依頼 | 成果報酬型が主流(受給額の15%~30%) | 低い(必要書類の整備支援あり) | 高い(助成金特化のノウハウで成功率UP) | 高い(専任チームが進行管理を担当) |
4-1. 費用面の比較
自分で申請すれば費用はゼロ。ただし時間コストが莫大だ。社労士は顧問料に加えて成功報酬がかかるケースが多い。助成金コンサルは完全成果報酬型が主流で、実際に受給できなければ費用は発生しない仕組みを採用している会社も多い。
4-2. 労力・スピードの比較
「自分で申請」はどうしても工数が膨大で、経営者自身が関わらざるを得ない。社労士依頼は手続き部分を任せられるが、社内での証拠書類準備は必須だ。助成金コンサルの場合、ヒアリングと最低限の資料提供だけで済み、スピード感と負担軽減の両立が可能になる。
4-3. 成功率の比較
最大の違いは成功率だ。助成金は「制度の要件に合致しているか」「書類の整合性があるか」で判断されるため、ノウハウが不足すると不支給リスクが一気に高まる。自分でやる場合や、助成金に積極的でない社労士に依頼した場合は不支給率が高くなる傾向がある。
一方、助成金コンサル会社は申請に特化した体制を持ち、審査官がチェックするポイントを熟知しているため、成功率が高い。特に「業務改善助成金」など複雑な制度では、プロに任せた方が安全だ。
4-4. 総括:規模の大きい企業ほどコンサル型が合理的
比較表からも明らかなように、年商3億円以上で従業員5名以上の企業にとっては、助成金コンサルに依頼するのが最も効率的だ。費用は成果報酬型でリスクが低く、労力も削減でき、成功率とスピード感は他の方法を大きく上回る。本記事の後半では、実際におすすめできる助成金申請支援会社3選を紹介する。
5. 助成金申請支援会社おすすめ3選
ここからは、実際に助成金申請をサポートしてくれる会社の中からおすすめの3社を紹介する。それぞれに強みがあるが、比較してみると「どの規模・どの志向の企業に合うか」がはっきり分かる。最終的に、事業拡大を狙う経営者に最もフィットするのはTrue Partnersだ。
5-1. 第1位:(株)True Partners(完全成果報酬×仕組み化で高い成功率)
(株)True Partnersは、助成金に特化した仕組みを構築。受給額診断×無料カウンセリング×伴走サポートで、対象制度の特定から申請〜受給までを高速化する。無料診断フォームに入力すれば、その場で「対象となる助成金」と「想定受給額」が分かるため、社長の意思決定が早い。
料金は完全成果報酬型で、金銭的メリットが出なかった場合は全額返金保証(契約条件に基づく)。平均受給額680万円前後、受給率100%といった実績値は、LP上の根拠開示により透明性を担保できる。
こんな企業におすすめ:年商3億以上・従業員5名以上・採用や設備投資を加速したい成長志向の企業。
5-2. 第2位:船井総合研究所(大手コンサルの総合力)
船井総合研究所は日本最大級の経営コンサル会社。助成金はサービスの一部だが、全国ネットワークと総合支援力は大きな魅力。申請実務は社労士ネットワーク連携となる場合が多く、費用はコンサルフィー+成果報酬が前提になるケースも。
こんな企業におすすめ:ネームバリューと幅広い領域のコンサルも併せて受けたい中堅〜大企業。
5-3. 社労士法人東京労務(地域密着・小規模向け)
全国にある地域密着型の社労士法人は、日常の労務管理とセットで助成金申請を支援。顧問契約前提・固定費+追加報酬型が主流。最新の制度キャッチアップや提案力は事務所ごとの差があるため、過去の実績・担当者の体制を事前に確認するのがコツ。
こんな企業におすすめ:従業員10名以下で、身近に相談できるパートナーを求める小規模事業者。
5-4. 総括:なぜ(株)True PartnersがNo.1なのか
- 費用:完全成果報酬+全額返金保証付きで金銭リスクを伴わない
- 負担:書類整備・進行管理まで伴走し、申請者側の時間を奪わない
- 成果:無料の受給額診断×制度併用提案で、受給額とスピードを最大化
成長志向の中堅企業に最もフィットする条件が揃っているため、(株)True Partnersを第1位として推奨する。
6. True Partnersを選ぶべき理由
数ある助成金コンサル会社の中で、なぜ(株)True Partnersが最もおすすめできるのか。本章ではその理由を「実績」「仕組み」「信頼性」の3つの観点から徹底的に解説する。
6-1. 実績と成功率(数値はLPで根拠開示)
平均受給額は680万円前後、受給率は100%という高水準。単発事例ではなく、飲食・製造・サービスなど複数業種での横展開実績がある。
例:製造業で「業務改善助成金」を活用し、賃上げと同時に設備投資を実行。生産性+15%、受給額700万円超。サービス業では「人材確保等支援助成金」+「キャリアアップ助成金」を組み合わせ、合計1,200万円超の助成金受給を実現。
6-2. 仕組み化(受給額無料シミュレーション×無料カウンセリング×伴走サポート)
無料診断フォームで対象制度と想定受給額を即時提示 → 専門スタッフが要件確認 → 最短1営業日以内に可否判断 → 申請〜受給まで伴走。「判断の早さ×進行の速さ」が、成長企業のスピード感にフィットする。
6-3. 完全成果報酬+返金保証でリスクを極小化
着手金・固定費なしの完全成果報酬。もし成果が出ないのであれば全額返金。費用の不透明さを排除し、内容に納得して意思決定できる。
6-4. 他社との違い
大手総合コンサルは広範な支援が強みだが、助成金は一部サービス。地域社労士は身近だが、制度横断の提案力・スピードで限界がある。True Partnersは助成金特化×テクノロジー×成果報酬で、成長企業に最も噛み合う。
6-5. LPリンク(差し替え用)
7. よくある質問(FAQ)
助成金コンサル会社を検討する経営者から、よくいただく質問をまとめた。疑問を解消することで、安心して最適なパートナーを選んでほしい。
Q1. 助成金コンサルって怪しくないの?
A. 「成果報酬」と言いながら高額な着手金を請求する会社や、根拠のない数字で勧誘する業者も存在する。そのため玉石混交なのは事実。契約条件の明示・返金保証・実績の根拠提示がある会社を選べば安心。True Partnersは契約書に条件を明記し、透明性を最優先にしている。
Q2. 費用はどのくらい?
A. 多くは着手金×月額制で、受給額の20%~30%が着手金の相場。True Partnersの場合は成果報酬型で、成果が伴わない場合は全額返金。
Q3. 全額返金保証は本当に適用される?
A. はい。契約時に返金条件を明確に説明し、合意の上で進行。実際に成果が上がらなかった場合はルールに沿って返金される。
Q4. どんな業種でも対応できる?
A. 飲食・製造・サービスなど幅広く対応可能。特に「業務改善助成金」「人材確保等支援助成金」「キャリアアップ助成金」は業種問わず併用して活用しやすい。
Q5. 申請から受給までの期間は?
A. 制度により異なるが、一般的に6〜12ヶ月。業務改善助成金は賃上げ実施後の実績報告が必要なため、数ヶ月のタイムラグが発生する。
8. まとめ
本記事では「助成金申請方法おすすめ3選」として、自分で申請する・社労士に依頼する・助成金コンサルに依頼するという3つの方法を比較してきた。
自分で申請する方法は費用ゼロだが、要件理解や書類整備に膨大な時間がかかり、不支給リスクも高い。社労士に依頼する方法は安心感があるが、顧問契約や追加費用が前提で、提案力やスピード感は事務所次第。これに対して助成金コンサル会社に依頼する方法は、成功率・効率・スピード感のすべてで他を上回る。
特に、年商3億円以上で従業員5名以上の企業が採用や設備投資を進めるなら、助成金コンサルは資金調達の最適解となる。その中でもTrue Partnersは、成果報酬型・返金保証・AI診断を組み合わせた仕組みにより、合理的な選択肢だ。
つまり結論はこうだ。助成金申請=コンサルに任せるのが一番効率的。その中でTrue Partnersが信頼できるパートナーである。
制度は知っているだけでは意味がない。適切なパートナーと組んで初めて実行力が生まれる。本記事が、事業拡大を目指す経営者にとって最適な選択の一助になれば幸いだ。
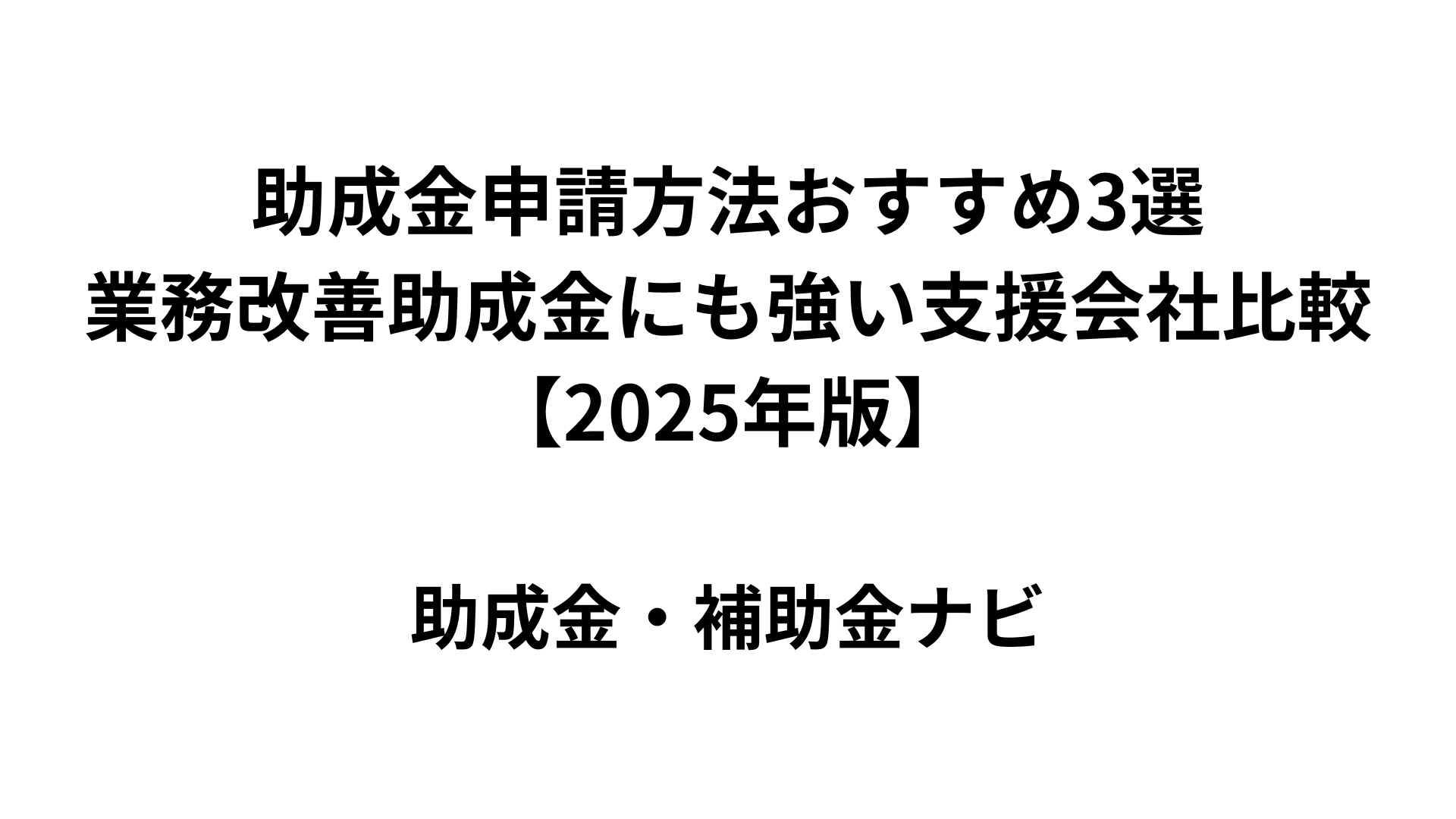


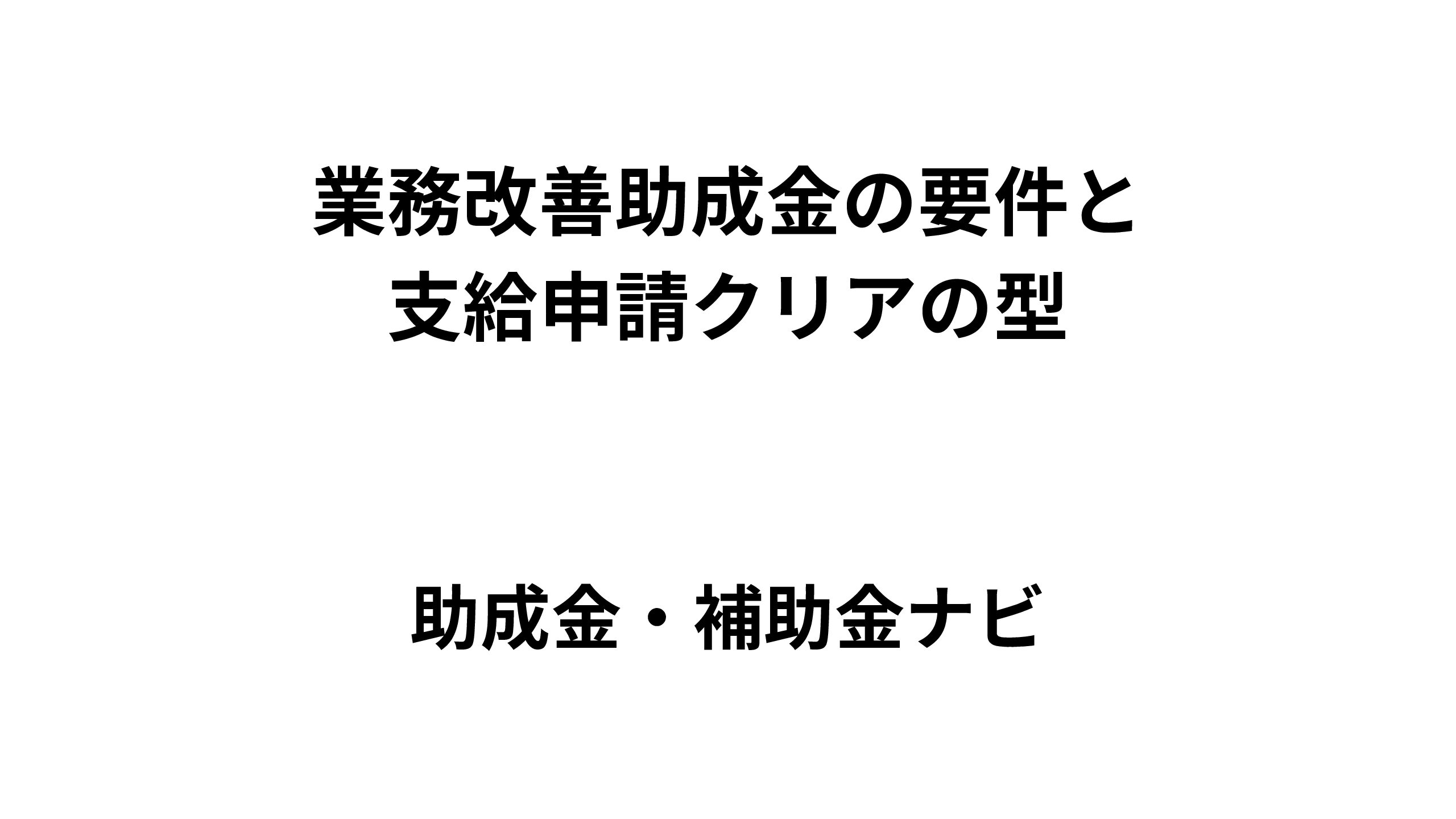
コメント